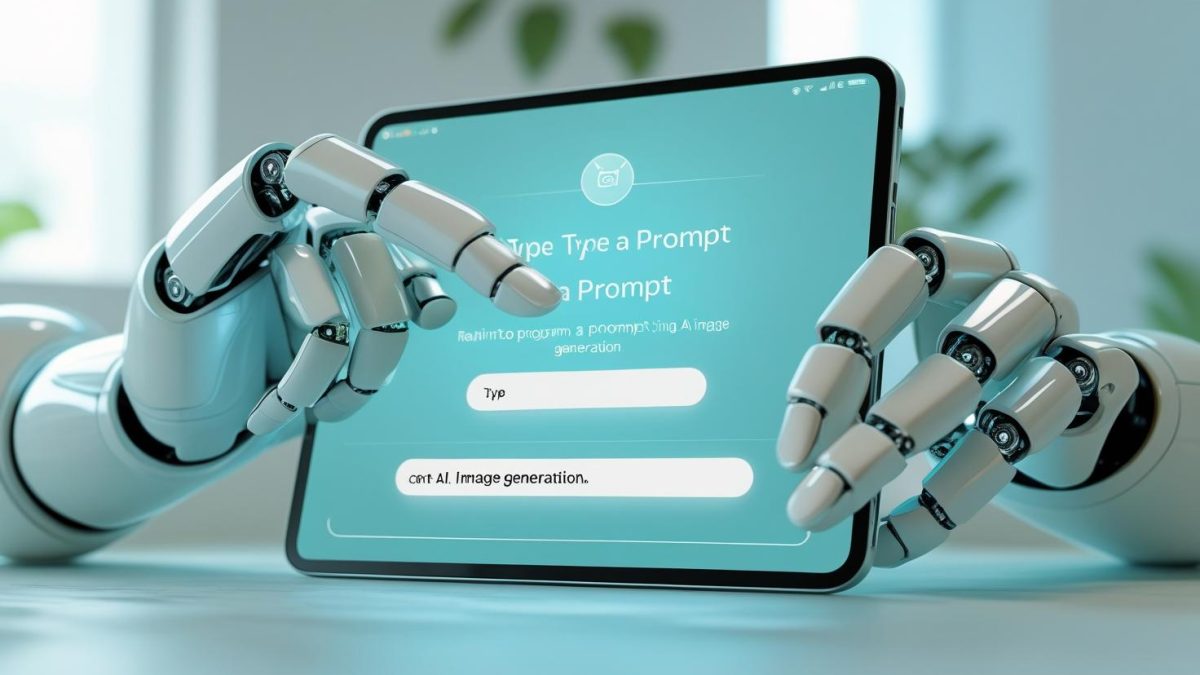はじめに
こんにちは、木暮太一です。
今日も「出版の裏側」についてお話していきます。
今回のテーマは、著者がAIをどう使って仕事を進めていくか。
このテーマ、きっと気になっている方も多いと思うんですよね。
だって正直な話、ラクしたいじゃないですか。
早く終わらせたいじゃないですか。
AI、使えるなら使いたいですよね。
では実際のところ、著者としてAIをどう活用するべきか?
その点を今日は具体的にお話していきます。
著者がAIを使ううえでの“使える”ところと“使えない”ところ
今、ChatGPT、Claude、Geminiなど、いろんなAIがありますよね。
正直なところ、AIが使える領域と、使えない領域ってハッキリ分かれています。
使えないところ:ベストセラー分析は頼れない
たとえば、「どんな本が売れてるか?」というベストセラーの分析。
これ、AIにいろいろ聞いてみたんですが、正直全然使えません。
AIが出してくるのは、100万部、50万部といった超ベストセラーの本ばかり。
もちろんそれらも勉強にはなりますが、自分の業界でピンポイントに売れている3万部、5万部の“リアルなヒット本”は出てこないんですよ。
つまり、自分のジャンルで何が評価されているか?
これをAIに分析させるのは、今のところは無理。
「ネタ」「切り口」「市場で評価されてるもの」──それらをAIに聞いても、出てくる答えはかなりズレているので注意が必要です。
AIで“使える”2.5のこと
一方で、「ここは使える!」というポイントもあります。
僕の感覚としては、大きく2つ、プラスおまけで0.5、つまり2.5個です。
① 章立ての構成をAIに任せる
本を書くうえで一番難しいのが、章立てを作ることなんです。
- 第1章では何を書く?
- 第2章では何を伝える?
- 各章の中でどういう項目を入れる?
これがしっかり決まれば、原稿はもうほとんど出来上がってるようなものなんですよね。
章立てができれば、あとはその内容を自分で書いてもいいし、AIに埋めてもらってもいい。
多くの著者がここでつまずいて「書けない……」って悩んでしまう。
でも、ここをAIに手伝ってもらうのはアリです。
自分一人で考えるより、圧倒的に早く構成を出してくれます。
② 切り口を明確にする
「切り口は自分で決まってるから大丈夫」
──と思ってる方、要注意です。
その切り口、99%アバウトすぎます。
これは内容が悪いとか、クオリティが低いって話じゃありません。
焦点がボヤけてる。だから伝わらない。
実際、僕の講座にはこれまで約2500人の受講生がいましたが、最初から出版レベルで切り口が定まっていた人はゼロです。
なぜかというと、出版業界の「特定する感覚」と、日常会話の「ぼんやりした伝え方」ではレベル感が全く違うからなんですよ。
セミナーやLP(ランディングページ)ではふわっとしてても何となく伝わりますが、書籍ではそれは通用しない。
超・具体的に特定する必要があります。
例:コミュニケーションの本を書きたい場合
- 「褒め方について書きたい」→ まだ広すぎる
- 誰が誰を褒める? 上司が部下? 親が子?
- 目的は? モチベーションUP? メンタルケア?
このように、一つのテーマでも何通りも企画が分かれるんです。
だから、アバウトだと思われたら即アウト。
「これとかこれとか言いたいんです」は通用しません。1個だけに絞る。
そしてこの切り口の特定作業をAIにやらせるのは非常に効果的。
AIに聞いてみると、「お、これは伝わるな」という焦点が見えてきます。
「私、できてるから大丈夫」と思わず、AIの力を借りてみるのがオススメです。
+0.5:出版企画書の目次案もAIに手伝わせる
出版企画書を書く際に「目次案」も添えるんですが、ここも間違って書いてる人が非常に多いんです。
実際の本の目次と、企画書の目次案は別モノです。
実際の本の目次は「〇〇というノウハウは何ページに書いてありますよ」という“案内板”のようなもの。
でも、企画書にはその“案内板”しか書かれていないと、肝心の中身が伝わらないんですよ。
編集者はこの目次案を見て、
- この人はちゃんと中身を持ってるのか?
- 文章を書けるのか?
そういうことを判断しています。
だから普通の本の目次のように書いたら絶対に通りません。
ここもAIに「こういうコンテンツで目次案を作りたいんだけど」と相談すると、かなり具体的にアウトラインを作ってくれます。
この記事のまとめ
AIは著者の強力なパートナーになりますが、使いどころを間違えると期待外れな結果になることも。
その中で、実際に使えるポイントとそうでないポイントを明確にしておくことが超・重要です。
- ベストセラーの傾向分析をAIに任せるのはまだ早い。
リアルな市場感までは拾いきれないため、ここは人間の感覚とリサーチ力が必要。 - 一方で、章立ての構成づくりはAIの得意分野。
ゼロから考えるより、AIのアイデアをもとに組み立てると爆速で形になる。 - 切り口の明確化もAIが頼れるポイント。
自分では絞り込んだつもりでも、客観的に見るとボヤけていることが多い。
AIとの対話で焦点を絞るべし。 - 出版企画書の目次案づくりもAIを活用。
単なる見出しではなく、「この著者には中身がある」と思わせる説得力が必要。
その設計をAIに手伝ってもらうのはかなり有効。
つまり、「全部AIに任せればいい」ではなく、「得意分野だけ使う」が正解。
AIはあくまで共同作業のパートナー。
上手に“部分委託”して、著者の価値を最大化することが、これからの出版ではますます大切になってきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
出版に興味がある方は、ぜひ【出版切り口診断】を受けてみてください。無料でやってます。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!
この記事内容の詳細をYoutubeで語っています。ぜひYoutubeもご覧ください。