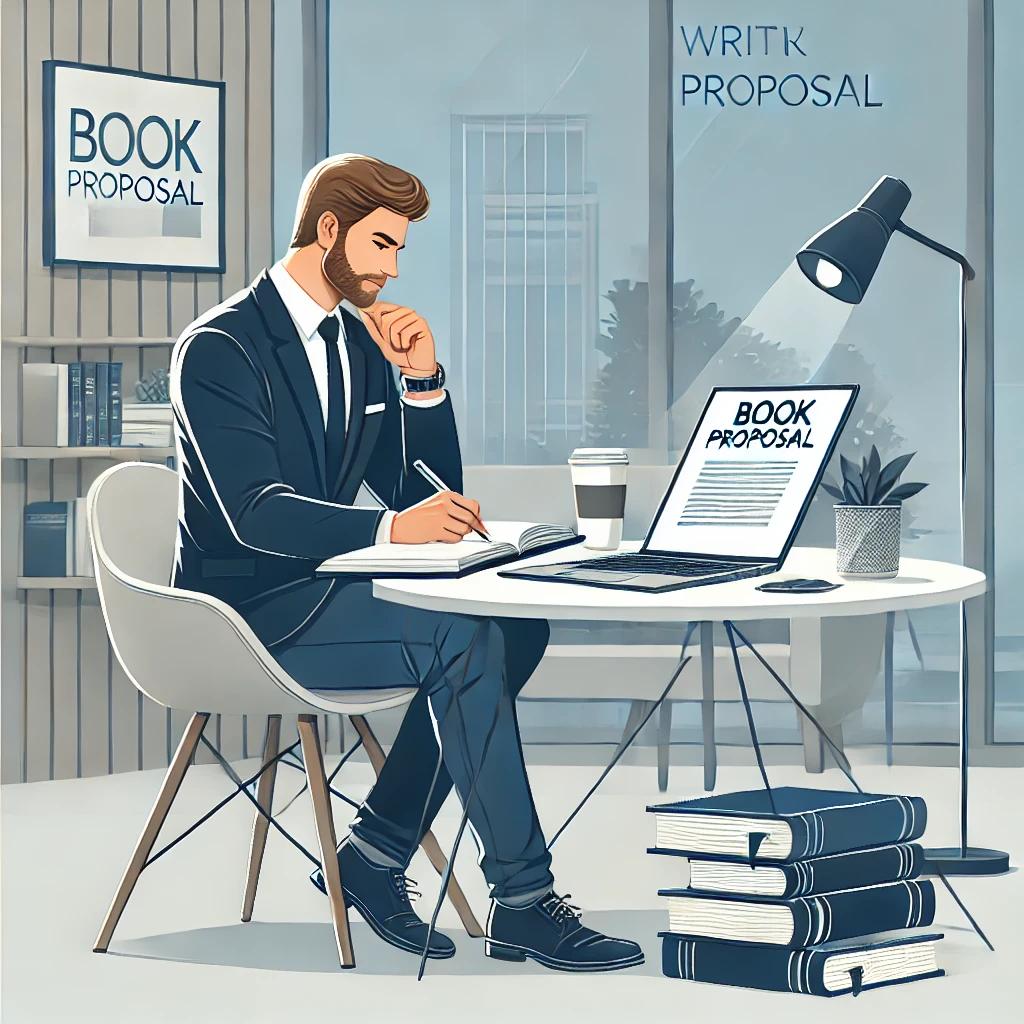はじめに
こんにちは、木暮太一です。
商業出版を実現したいときに出版企画書を書くんですが、この出版企画書の書き方が皆さんずれているんです。だから出版が実現しないんですね。今日は出版企画書についてお話しします。
出版企画書というのは、私たちが本を出そうと思った時に、編集者に対して提案する資料のことなんです。
私が考えていることはこんな感じで、こういう本を作りたいですという提案資料なんですね。この出版企画書を書かないと、そもそも始まらないんです。
編集者とどんな出会い方をしたかは関係なく、この出版企画書を作らなければいけないんです。
誤解その1:一般的な企画書との違い
ただですね、出版企画書の書き方が、皆さんずれているんです。これはかなり誤解があるからなんですが、大きく二つの誤解があるんです。
一つ目の誤解は、ビジネスパーソンで経験を積めば積むほど、自分の事業で「企画書」を書いた経験のある方が増えてくる。そのためビジネスで作成したことのある企画書と同様のものを作ればいい、と思う方が増えるということなんです。
自分が過去に書いた商品やサービスの企画書とか、世の中で書かれているものを見たことがある方は、それと同じような感じで書けばいいのかなって暗黙の了解みたいなものを持つんですね。これはすごく自然なことなんです。
出版企画書ではなく、ビジネスで作成するような一般の企画書を見て、出版したい人が書くのが出版企画書なんだなって考えて、自分が書きたい本のまとめみたいなものを書けばいいと考えちゃうんです。
なぜ一般的な企画書では通らないのか
発想としてはすごくよく分かるんですけど、だからこそ通らないんです。出版企画書には編集者が知りたい内容を伝えないといけないんです。
編集者が知りたいのは、皆さんがどんなテーマを書きたいかじゃなくて、どんなノウハウを持っているかということなんです。コミュニケーションについて書きたいから採用するってことじゃなくて、その人が持っているコミュニケーションに関するノウハウを知りたいんですよ。
つまり、細かい部分まで会話しないといけないのに、多くの方が概要で終わっちゃってるんです。それは、一般的な企画書が概要をまとめて出すものだからなんですね。発想としては自然なんですけど、そのために編集者から認められないという結果になっちゃうんです。
誤解その2:編集者視点のズレ
二つ目のズレについてですが、私は商業出版のコンサルティングをしているんですが、私と同じように商業出版のアドバイスをされている編集者の方がいらっしゃるんです。
編集者がその経験を活かして、商業出版のアドバイスをしているってことになるんですが、実はこれも出版社目線とは少しずれちゃうことがあるんです。
出版の二段階構造
編集者は現場でやってきたんだから、その人たちが教える出版企画書はずれているわけがないって思うかもしれないんですけど、これが違うんです。たぶん本人たちも気づいていないと思うんですが、出版には二段階あるんです。
まず一つ目は出版社に認められて出版決定になるところまでで、そして出版が決まったら、実際にその本を作って、読者に評価してもらえるか、つまり買ってもらえるかという段階があって、それが二段階目なんです。
編集者と著者の視点の違い
編集者が考えているのは、読者にどうやって売るかということなんです。つまり、上で説明した内容でいうと二段階目ということになります。
出版社は自分たちが決めたものが読者に響くかどうかを考えているんですね。それは中の人だからそう考えていいんですけど、私たちは出版社の人間じゃないんです。
つまり、最初に出版社の人たちを説得して、その上で読者を説得しないといけないんです。その一段階目となる「出版社の人を説得する」ということもするのが、出版企画書です。
正しいアプローチとは
私たちはまず編集者・出版社にOKをもらわないといけなくて、その後に読者にOKをもらわないといけないんです。でも、編集者はそもそも中の人だから読者のことを見ているんですよ。読者に響くかどうかを考えているわけなんです。つまり、編集者が作ろうとしている企画書は、読者に受けるための企画書なんです。
センター試験と二次試験の例え
私たちは読者にOKをもらう前に出版社にOKをもらわないといけないんです。だから、私たちが作らないといけない出版企画書は、読者を見ちゃいけないんです。まずは編集者・出版社を見ないといけない。そこが第一関門だからなんです。センター試験と二次試験みたいなものですね。
就職活動の例え
就活の例で言うと分かりやすいかもしれません。転職でもいいんですけど、まずはその会社に入らないといけないですよね。その後にエンドユーザーが求めることを、自分たちの顧客が考えることを認めて実行していくんです。つまり、まずは面接に通らないといけないんです。
面接の時に、エンドユーザーのことばかり話しちゃうと、よほどうまく話せる場合を除いて、見ている方向が違っちゃうんです。判断するポイントが違うし、判断する人も違うから、それじゃあ失敗しちゃうんです。
まとめ:出版実現への道筋
能力がなくて断られるんじゃなくて、提出する資料が違うから断られちゃうんです。ここを認識していないと、たぶんいくら頑張っても本は出版できないと思います。出版企画書というのは、出版を実現させるための資料なんです。そのつもりで作らないといけないんです。
今日は概念的な話をしましたが、実際に私の講座では、読者じゃなくて出版社に認められる出版企画書の書き方を教えています。これは、私が著者であり出版社を経営しているからできることでもあるんです。
このやり方を身につければ、皆さんの今までのノウハウや知識が変わらなくても、一気に話が前に進んで、出版が実現するんです。出版が実現しない方は見ている方向が違うんです。提出する資料が違っていただけの話なんです。
正しく作戦を練って、正しく行動すれば、商業出版は実現できます。このチャンネルでは、商業出版に関する様々なノウハウや知識を出していますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最後まで見ていただき、ありがとうございました。