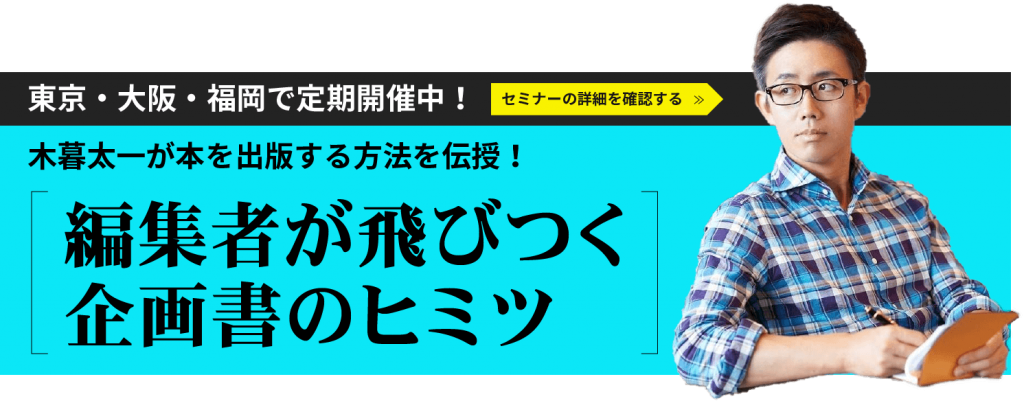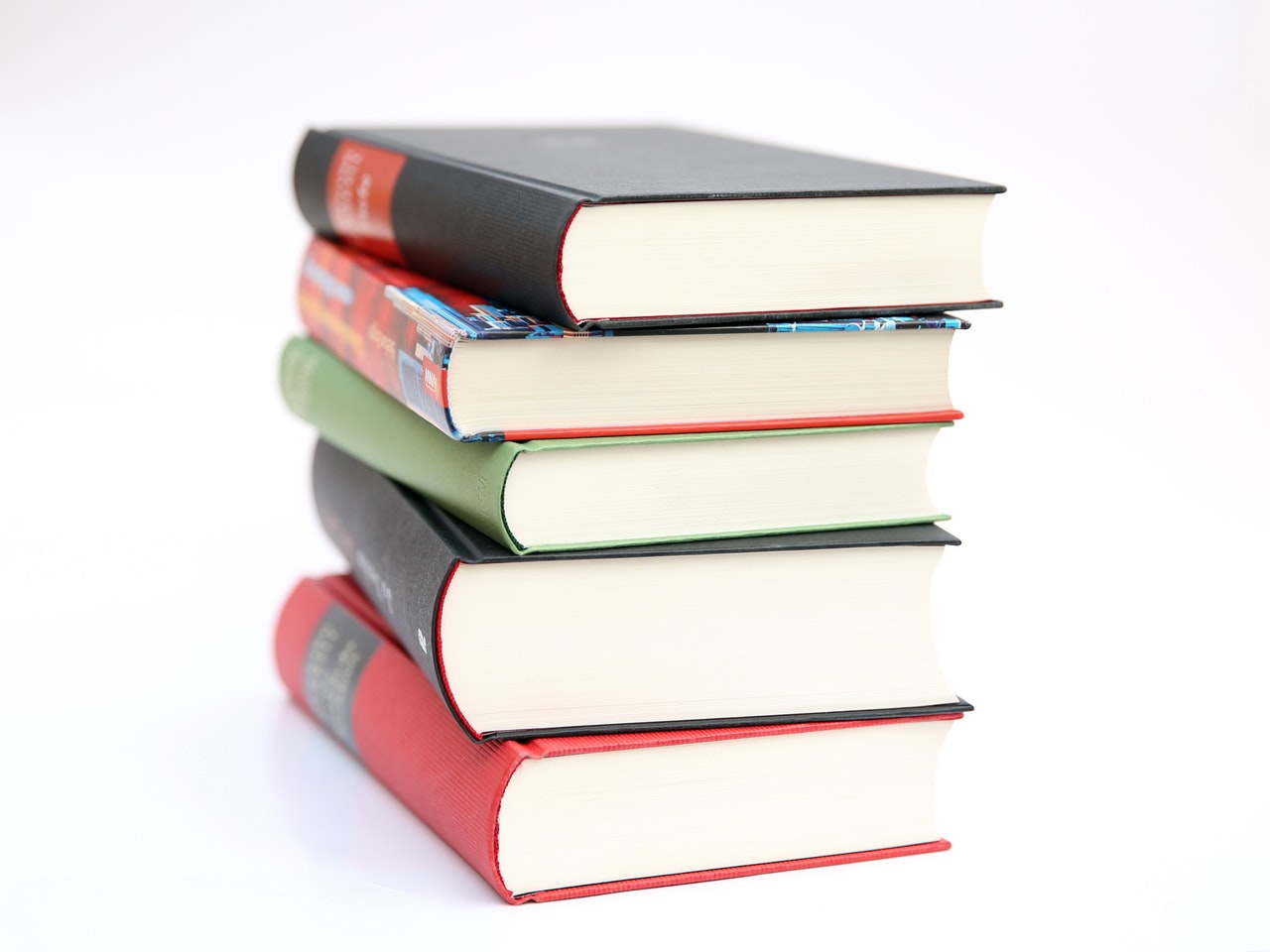こんにちは、木暮太一です。
今日は「増刷」とは何か、重版や増版との違い、本が増刷されるロジックなどについて説明します。
「増刷」とは?
2018年にぼくが出版した『働き方の損益分岐点』(講談社文庫)が増刷になりました。
そして2017年の春に出した『どうすれば、売れるのか?』(ダイヤモンド社)も、またまた増刷されたようです。
増刷とは、「もっと印刷する」ということで、
要は「売れているから、もっと刷る」という意味です。
「重版」と「増版」の違い
厳密にいうと、この2つはニュアンスが異なります。
「重版」は、内容はほぼ変えずに再び印刷すること。
誤字脱字などの微修正は入ることもありますが、内容の変更はありません。
「増刷」というと、こちらの重版と同義になります。
「増版」とは、内容に手を加えた上で再び印刷することです。
「改訂版」「第2版」などと表記されるのは、「増版」に分類されます。
重版される目安・基準は?
「本を出すなら増刷を目指さないと」
「3刷(=2回増刷)になったらホンモノですね」
などなど、よく言われています。
著者としても「増刷」はとてつもなくうれしいことだし、
もしかしたら出版することよりも増刷の方がテンションあがるかもしれません笑
ただ、ほとんどの著者は
どうすれば増刷されるかがわかりません。
「増刷されたら超うれしい!」と言いながらも
何をすればいいか自分ではわからないんです。
これでは作戦が立てられませんね。
なので今日は「増刷されるロジック」について
細かく解説します。
結論としては、
①いろんな書店からどんどん追加注文が来て、出版社からどんどん書店に出荷していること
②毎日本が売れていて2週間で擦った冊数の25%くらいが読者に渡っていること
この2点が指標になります。
詳しく見ていきましょう。
本が増刷されるのは「出版社に在庫がなくなった時」ではない
まず、本が増刷されるのは、
「出版社に在庫がなくなった時」ではない、ということです。
え!? そうなの???
・・・・・
・・・・
・・・
じつは、そうなんです。
「足りなくなったから増刷する」のでは? と感じるかもしれませんが、
それは違います。
出版業界は「返品」が可能なので、
日々、書店に並んでいた本が出版社の倉庫に戻ってきます。
そのため、いま在庫がなくても、
来週には結構な数が返品されて在庫ができることもあります。
なので出版社は、
手持ちの在庫がゼロになったからと言って
即増刷をするわけではありません。
出版業界は「注文」が2段階に分かれている
また、出版業界は「注文」が2段階に分かれている
ということも知らなければいけません。
| 第一段階 | 書店が出版社に注文する 本は、書店が出版社に注文し、店頭に並べます。この段階で出版社の在庫は減ります。でも、その段階ではまだ売れていませんね。 |
| 第二段階 | 読者が書店で買う 書店に並んでいる本を読者がお金を出して買えば、そこでようやく「売れた」となります。 |
第一段階をクリアーしても、
第二段階で読者に買ってもらえなければ
やがて返品されてしまいます。
第二段階は超重要ですね。
かといって、
読者からの需要が見えていても、
書店に本を並べられなければ売れません。
たとえば、テレビで紹介されて
一時的にすごく注目が集まったとします。
そんな時、本屋さんに置いてないから売れずに機を逃す
ということはよくあります。
出版社にとって大切なのは、
どんどん書店に出荷されて(第一段階クリアー)
さらにどんどん読者に売れている(第二段階クリアー)
という2つの状況が必要なわけです。
第二段階を判断する「POSデータ」
そして、この第二段階を判断するのは
「POSデータ」です。
出版社といえども、
自社の本がどれだけ実際に売れているかを
追いかけることはできません。
なので、書店チェーンや取次(問屋)が提供している
POSデータを買い、それを見て判断するんです。
このPOSデータでは、
「発売後2週間で、25%消化」が一つの目安とされます。
「最初に流通させた部数が、当初の2週間で25%売れる」
ということです。
ここまで行けば、増刷が検討されます。
ただ、同時に「第一段階(出版社→書店)」の部数も
考慮しなければいけませんね。
いくらPOSデータ上で売れていたとしても、
一部の本屋さんで売れているだけで、
別の本屋からは大量に返品が来ているのであれば
増刷はされません。
増刷が判断されるポイント
となるとポイントは、
1)いろんな書店からどんどん追加注文が来て、
出版社からどんどん書店に出荷していること
2)POSデータで見たとき、毎日毎日ちゃんと本が売れていて
2週間で25%くらいが読者に渡っていること
の2つになります。
こうなったら増刷される可能性は非常に高まります。
著者はこの状態を目指さなければいけないし、
なんなら、自分でこの状態を作り出せなければいけません。
重版される流れ
では、どのような流れで重版の判断がされていくのでしょうか。
流れ①発売直後の売れ行きを出版社がチェック
書店の初回注文数(配本数)や店頭での売れ行き(POSデータ)、Amazonなどオンライン書店の売上や在庫状況などから、売れ行きをチェックします。
流れ②在庫が一定数を切ったら検討開始
初版の在庫が一定数を切ると、営業部や編集部が重版の検討を始めます。
そして売れ行きが好調で、今後も売れる見込みが高ければ重版が決定します。
流れ③社内決裁と印刷手配
編集長や営業会議で正式に決定します。そして印刷所に追加印刷を依頼することとなります。
重版の決定に関して、多くの場合は出版社のほうで進めることとなるので、著者には「重版決まったよ!」と事後報告が入る形になります。
重版後はSNSでの発信や取材など、販促の中心になって活動することとなります。
重版される本の秘訣
本を出版するなら、重版される本をつくるのが理想ですよね。
ここでどんな本が重版されやすいかご紹介します。
■明確なターゲットとニーズを捉えている
つまり読者層が明確で、「この本が必要」と感じさせる内容の本です。
例えば、「子育て世代向け」「料理初心者向けレシピ」など。自分に必要な本かどうかが一目でわかりますね。
■タイトルと表紙のインパクトが強い
書店やネットで目に留まるタイトルとデザインであれば、「なんか面白そう」「買ってみよう」となりやすいです。
一瞬で内容が伝わる、もしくは「気になる」と思わせる本は大事ですね。
■SNSや口コミで広がる
読者が「人に勧めたくなる」という内容も重要です。インフルエンサーや書評家の紹介があれば、大きな追い風になります。
「話題になっている本」であれば、読んでみたいと思いますよね。
■著者に発信力がある
もともと著名人であったり、またSNSやYouTubeなどでファンがいるインフルエンサーは拡散力が強いので、本を出せば注目が集まります。
■タイミングと社会の流れに合っている
社会的に話題になっているテーマの本は、読み手が多いです。
例えば生成AIについてだったり、防災についてだったり。特に社会問題や流行と重なると、一気に注目されることがありますね。
重版されるベストセラー作家になる方法
実際にどうやって第一段階、第二段階をクリアーさせるかは
ぼくの出版理論講座で徹底的に解説しています。
出版を成功させたい方はぜひいらしてください。