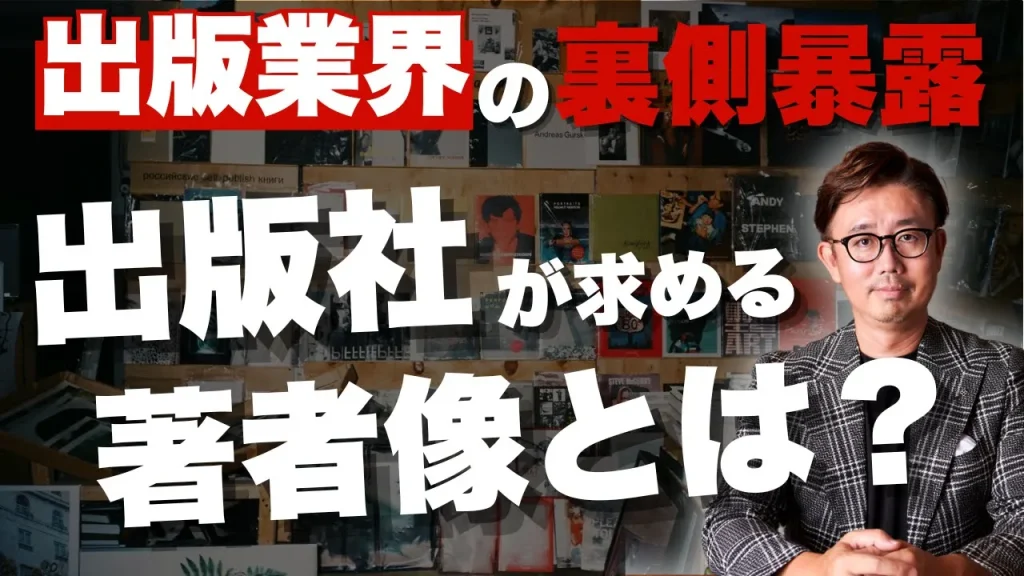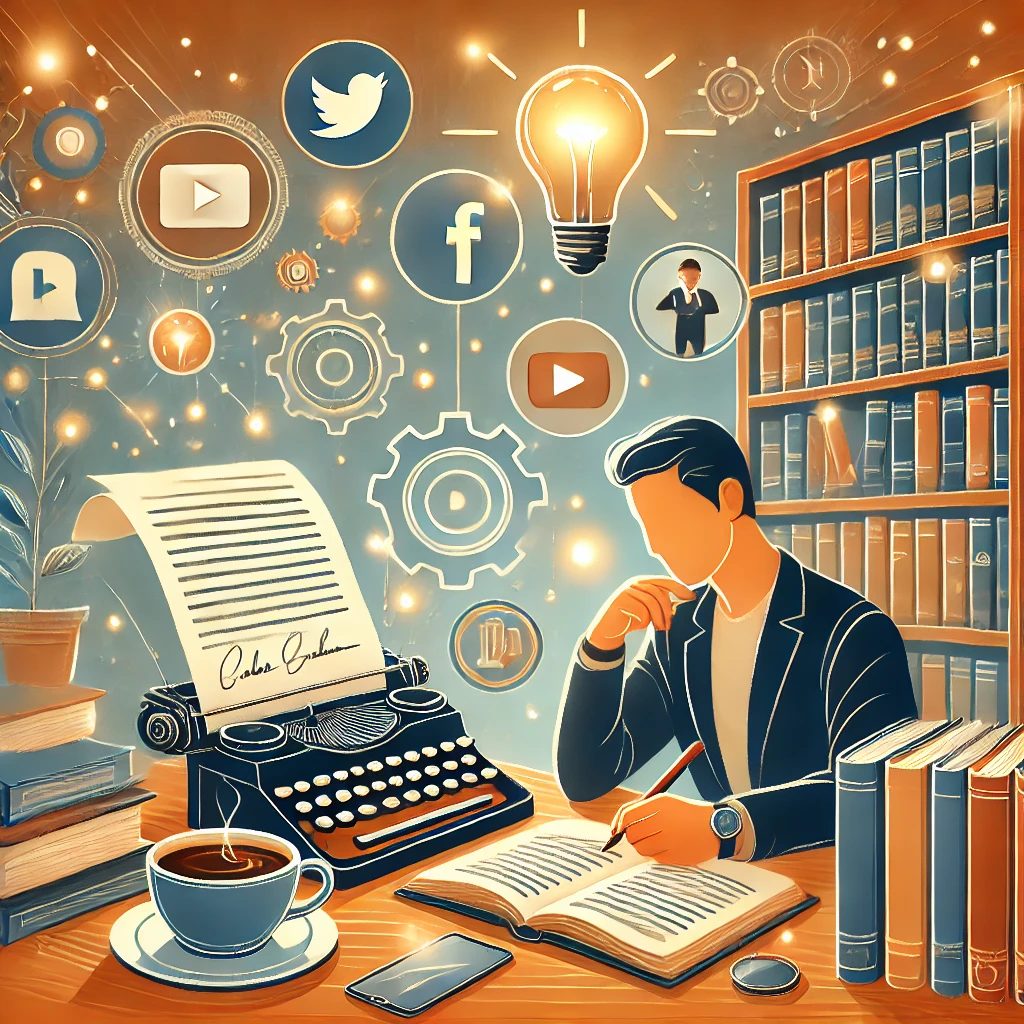はじめに
こんにちは、木暮太一です。今日も出版の裏側についてお話ししていきます。今回のテーマは、「出版社が求める著者像」 についてです。出版社がどのような著者を求めているのか知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
出版社は常に著者を探している
本を出すことは大変だと思われがちですが、実はそうでもありません。なぜなら、出版社や編集者は常に新しい本を出さなければならない からです。
編集者のノルマとして、毎月1冊の新刊を出す という目標が設定されていることが多く、それを達成するために、新しい著者やネタを常に探している のです。
しかし、ここで問題なのは、「本を出すこと」が目的になってしまっている こと。売れるかどうかは二の次で、新しい本を出しさえすればノルマ達成となるため、編集者の意識が「本を売ること」や「良いものを作ること」よりも「新しい本を出すこと」に向いてしまっているのが現状です。
とはいえ、新しい本を出さないと出版社のビジネスが回らないのも事実。そのため、編集者がどのような著者を求めているのかを理解し、それに合ったアプローチをすることが重要になります。
出版社が求める著者の3つの特徴
出版社が著者を探す際、大きく分けて3つのパターン があります。
1. 拡散してくれる著者
出版社にとって、自分の本を宣伝してくれる著者は非常にありがたい 存在です。例えば、SNSやYouTubeなどのプラットフォームで拡散できる著者は、出版社にとってプラスになります。
しかし、ここで誤解しないでいただきたいのは、
「SNSで告知すれば売れる」わけではない
ということです。
SNSのフォロワーが多いからといって、本が売れるとは限りません。例えば、YouTubeの登録者が100万人いたとしても、そのうち本を買う人は1000人程度にとどまることもあります。
つまり、SNSのフォロワー数が多いことは必須条件ではなく、それだけでは決定打にならない ということを理解しておくべきです。
2. 文章が書ける著者
文章が書ける著者は、編集者にとって非常に便利な存在 です。
出版社は多くの本を出したいと考えていますが、著者の執筆スピードが遅かったり、文章をうまく表現できなかったりすると、スケジュールに影響が出てしまいます。
そのため、「書ける著者」=「重宝される著者」 という構図が成り立ちます。
また、たくさん本を出している著者が必ずしも売れているわけではありません。売れていなくても本が出せる理由は、「出版社にとって都合がいい著者」だから です。
つまり、
文章が書ける人であれば、次々に本を出せる可能性が高い
ということです。
「売れているから次の本が出る」のではなく、「文章を書けるから次の本が出る」 という側面があることを理解しておくと良いでしょう。
3. 言葉を持っている著者
ここでいう「言葉を持っている」とは、「著者独自の視点や考え方を持っている」ということ です。
例えば、「働き方」について語る場合、多くの人が「時短」「強みの発掘」「好きなことを仕事にする」といった、一般的なテーマに触れます。しかし、それでは読者にとって新鮮味がなく、興味を引きません。
一方で、独自の視点や考え方を持っている著者は、出版社にとって非常に価値が高い のです。
私自身が過去に出した「僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか」という本は、カール・マルクスの『資本論』の理論をベースに、現代の働き方を説いた ものです。
「なぜこんなに頑張っているのに給料が上がらないのか?」
という疑問に対して、資本主義のルールを踏まえて説明 したところ、非常に注目され、大ベストセラーになりました。
つまり、
独自の視点を持ち、それをわかりやすく伝えられる人が、出版社に求められる著者
なのです。
ただし、読者が求める範囲内で独自性を発揮すること も重要です。いくら個性的な意見を持っていても、読者が求めていなければ意味がありません。
この記事のまとめ
出版社が求める著者には、以下の3つの特徴があります。
- 拡散してくれる著者
- SNSでの告知はメリットになるが、それだけでは本は売れない。
- 文章が書ける著者
- 執筆スピードが速いと、出版社にとって重宝される。
- 言葉を持っている著者
- 独自の視点や考え方を持っていることが大切。
この3つを意識しながら、コンテンツを作り、望まれる著者を目指していきましょう。
この記事内容の詳細をYoutubeで語っています。ぜひYoutubeもご覧ください。