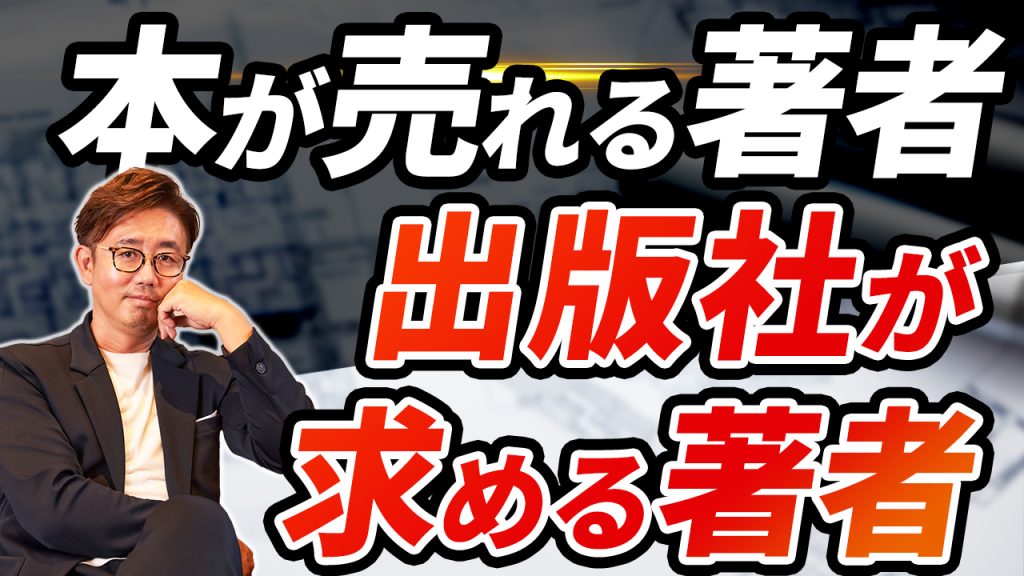こんにちは、木暮太一です。
今日も「出版の裏側」についてお話ししていきます。
今回のテーマはズバリ、
「本の売り方」と「出版社が欲しがる著者の要素」
です。
本は「こうすれば売れる」という単純なものではない
「本を売るには何をすればいいのか?」
これは多くの人が考えるテーマだと思います。
でも、結論から言ってしまうと、
何をやっても、基本的には本は売れません。
たとえば雑誌に紹介されたり、YouTubeでバズったり、Twitterで話題になったり……
そういうプロモーションがあったとしても、ほとんど本の売上にはつながりません。
実際に僕自身、雑誌の取材記事が出たタイミングで売上のデータを比較したことがあります。
でも、前後で売上がまったく変わらないんです。
YouTube、ラジオ、テレビでも売れない
僕もYouTubeでいくつかの番組に出させていただいています。
「ピボット3」とか「103」とか。
合計で再生回数は60万PV以上あると思います。
これだけ多くの人に見られているのに、
本はほとんど売れない。
「50万回再生されれば、5000人くらいは買ってくれるんじゃないか?」
そう思いたくなる気持ちはわかります。
でも残念ながら1000冊すら売れないんです。
ラジオもテレビも同じです。
出演したからといって売れない。
意味がないのかというと完全に無意味というわけではありませんが、単発で売上に直結することはないんです。
売れるのは「テキスト情報」
じゃあ何が効くのか?というと、テキストのプロモーションです。
ブログ記事や連載記事など「読む」メディアがバズると、本の売上にダイレクトに反映されます。
これが一番大きい。
僕の場合、ダイヤモンド・オンラインで「リーダーの言語化」や「すごい言語化」に絡んだ記事を書いていますが、記事がバズると確実に売上が上がるのがわかります。
記事公開のタイミングと実売数を全部チェックしていますから。
テキストと動画の大きな違い
SNSで拡散されるような短いテキスト(Twitterやインスタのリールなど)は、実はあまり読まれていません。
読まれるというより、「流し見」されている感じなんですね。
でも、長文の記事の場合は違います。
ちゃんと読んでもらえて、そこから「面白そう、この人の本も読んでみよう」となりやすい。
テキストからテキスト(本)への移行はスムーズなんです。
でも、動画からテキスト(本)に移るのは意外とハードルが高い。
SNSのフォロワー数が多いからといってそれが売上に繋がるとは限らないというのは、まさにこのためです。
出版社が評価する「本当に欲しい著者」とは?
出版社が求めるのは何か?
SNSのフォロワーが多いことを気にする出版社もありますが、それは正直「資産の切り売り」のように見えます。
「この人はこれだけフォロワーがいるから、その人たちに買わせよう」
そんな発想に近いんですよね。
でも本当に出版社が求める著者の条件は、長い文章が書ける人。
要するに、マラソンが走れる人です。
SNSで短い投稿をたくさん出している人、たとえばインスタグラマーやインフルエンサーが本を出しても、長文が書けなければ評価されにくい。
だからこそ、自分のブログや連載を持って長文で情報発信している人が強いんです。
SNSは「拝み倒しツール」くらいのつもりで使う
SNSがまったく無意味かというと、そうでもありません。
「すでにファンになってくれている人たち」に向けては意味があります。
その人たちに向けて、
「本当にお願いだから買ってください」
「拝み倒します」
と、訴えかける。
そういう使い方はアリです。
でも、それを前提に本を出すことを考えるのは本末転倒です。
雑誌の紹介記事では売れない
昔から変わりませんが、雑誌に紹介されても本は売れません。
雑誌の読者って雑誌のためにすでにお金を払ってるんですよ。
だからそこで「この本がいいですよ」って紹介されても、さらにお金を出して別の情報を買うことはあまりしない。
例外的に昔の書評欄で売れてた本もありますけど、ほんの一部です。
出版を目指す人へのアドバイス
これから出版を目指す方へ。
「SNSのフォロワーを増やすことに全力を注ぐ」のではなく、長文を書いて自分のノウハウをしっかり伝えることを意識してください。
編集者に出会ったときにも「ちゃんと長い文章が書ける人です」というアピールは重要です。
出版社が求めているのは「ちゃんと本を書ききれる人」なんです。
短距離走ではなくマラソンが走れる人。
この点、しっかり意識してアプローチしていきましょう。
この記事のまとめ
本の売上に直接つながるのはSNSや動画といった派手なプロモーションではなく、地道なテキストによる情報発信です。
特にブログや連載記事のように読みごたえのある文章が注目されることで、本の購買につながりやすくなります。
一方でSNSは既存のファンに向けて告知したりお願いする手段としては有効ですが、それを中心に据えた戦略では成果が出にくいのが実情です。
出版社が本当に求めているのは短く目を引く投稿を量産できる人ではなく、しっかりとした長文を書ききれる人です。
つまり一時的な注目よりも、継続的に価値を届けられる著者こそが評価されます。
また、雑誌やテレビなどの従来メディアによる紹介は影響がまったくないわけではないものの、本の売上に直結するケースは非常に限られています。
出版を目指すならまずは自分の言葉でじっくりと長文を書き、伝えたいことをしっかり形にする力を磨いていくことが重要です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!
この記事内容の詳細をYoutubeで語っています。ぜひYoutubeもご覧ください。