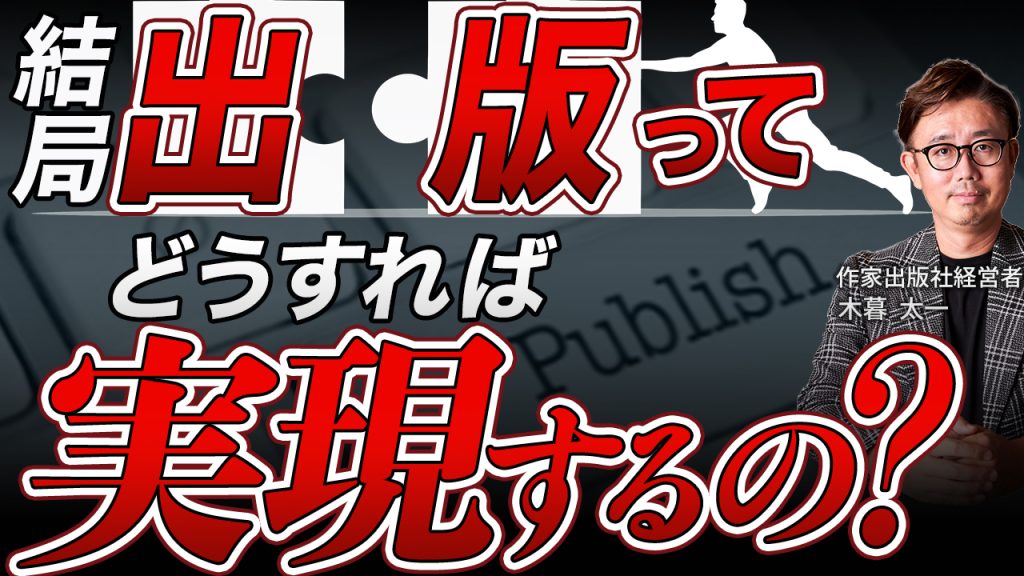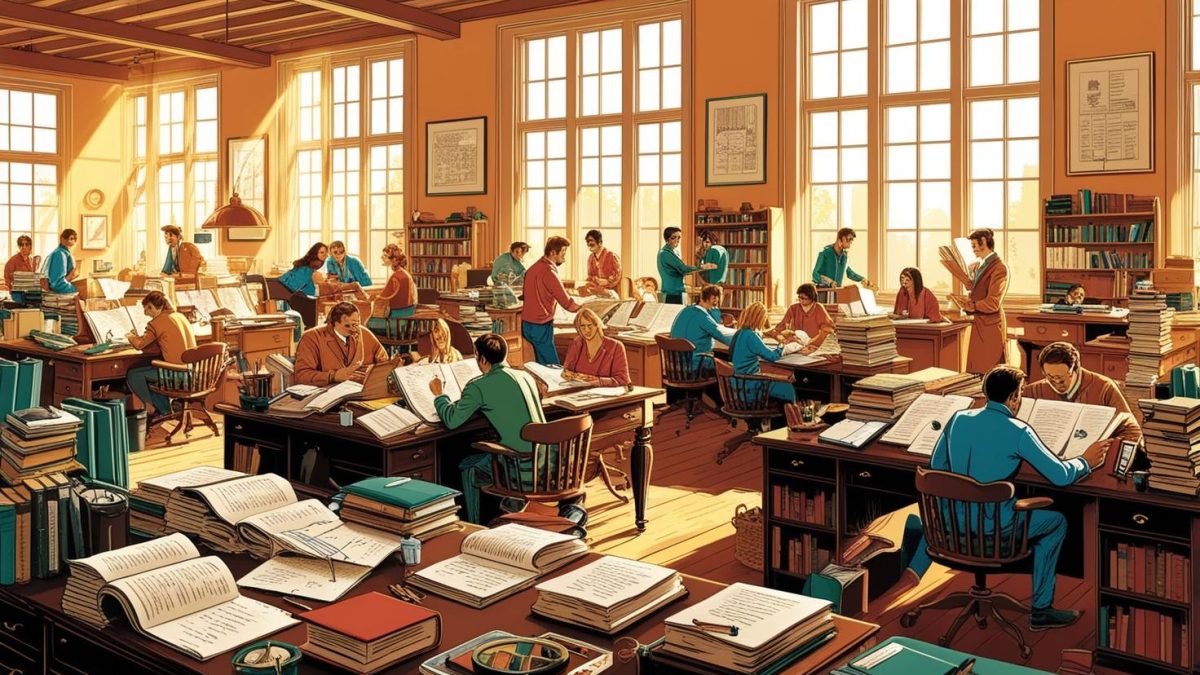はじめに
こんにちは、木暮太一です。
最近ようやく肩の調子が戻ってきまして、筋トレも本格的に再開しております。そんな中で今日も「出版の裏側」についてお話ししていきたいと思います。
今回のテーマは「出版って、そもそもどうすれば実現できるの?」という原点に立ち返る話です。
出版を目指す多くの人にとって非常に重要な話ですので、ぜひ最後までご覧ください。
出版のリアル:なぜ情報が少ないのか?
出版に興味がある方なら誰もが感じるはずです。
「出版って、どうすればできるの?」
「どうやって出版社に企画を通せるの?」
でも実は、正しい情報がなかなか手に入りません。
なぜかというと、正確な情報を持っているのは出版社側だけだからです。
著者として本を出している人でさえ、裏側の構造を知らないことが多いんです。
たとえ10年間本を出し続けていたとしても、それは表側の話に過ぎません。
自分の本がどうして採用されたのか、どのくらい売れているのか、どんなプロモーションが行われているのか――
これらは、著者にはほとんど知らされません。
著者が知らないプロモーションの裏側
たとえば僕は、ネット広告、雑誌、ラジオなどいろんなプロモーションを受けています。
実際、ラジオの取材も今朝受けてきたところです。
でも、正直言って「何が当たるか」はほとんど決まっています。
どのプロモーションが効果的か、それは著者には教えられないんです。
そのため多くの著者が、「派手に目立てば売れる」「斬新な企画なら通る」と思い込んでいます。
ですが――
それは誤解です。
出版と就活は似ている
出版を目指すなら、「出版は就活と同じだ」と考えてください。
就活を経験した方なら思い出してほしいのですが、自己分析や業界分析をして、
エントリーシートや履歴書を書いて企業に提出しますよね。
その書類が出版における「出版企画書」にあたります。
いい内容を書けるように自己分析を頑張ったり、たくさんの企業に出したりしましたよね?
出版もまったく同じなんです。
僕自身、就活時代には200社以上にエントリーして、最終的に内定を3社からもらいました。
その感覚が、出版と本当にそっくりなんです。
出版が決まるために必要な2つの要素
出版を実現するために必要なのは、この2つです:
① 質の高い出版企画書(資料)
ただし、ここで言う「質が高い」とは、
単に内容がいいという意味ではなく、
「出版社が望んでいる内容であるかどうか」
という視点が重要です。
自己満足な企画ではなく、相手のニーズにマッチしているかどうかが問われます。
② 出す相手とのマッチング
就活で「ご縁があれば…」というように、出版もマッチングが命です。
どれだけ優れた企画書を作っても、出す相手がズレていたら採用されません。
この「マッチング」が、著者にとって最も難しいポイントなんです。
多くの著者が抱える“勘違い”
「内容が良ければ、企画は必ず通る」
多くの著者がこのように思い込んでいますが、これは完全に誤解です。
就活と同じで、実力だけでは採用されません。
相手に伝わらなければ意味がないし、相手が求めていなければ通らないんです。
出版社や編集者とのマッチング精度
出版企画をどこに出すか。
これを間違えると、絶対に通りません。
出版社ごとにざっくりとした傾向はあります:
- 日経BP、東洋経済新報社 → ビジネス系が強い
- 主婦の友社、主婦と生活社 → 女性向け・家庭向けが多い
でも、「どの出版社がどんな本を本当に求めているか」は、外部の人間にはわからないのが実情です。
ましてや、「編集者が今何に興味を持っているか」なんて、著者には完全にブラックボックスです。
つまり――
素人がマッチングを判断するのは不可能なんです。
編集者との出会いがすべてを変える
出版社の中で企画を採用するのは、会社ではなく編集者個人です。
つまり出版とは、「企業とのマッチング」ではなく、「編集者とのマッチング」です。
その編集者が今どんなテーマに関心があるか。
何を必要としているか――
これがわからなければ、出版は前に進まないんです。
どうやってマッチングを実現するか?
このあたりのノウハウについては、僕の運営している「出版塾」の講座で詳しくお伝えしています。
出版を目指すなら、まずは正しい知識を身につけることが最優先です。
知識がなければ、僕のように商業出版に11年もかかるかもしれません。
あなたはいま何歳ですか?
11年後、何歳になっていますか?
僕と同じ遠回りをしないためにも、まずは体験セミナーで出版の正しい全体像を掴んでください。
この記事のまとめ
出版を成功させるには、
「出版企画書の質」×「編集者とのマッチング」
という方程式を理解することがカギです。
自己流ではうまくいかないからこそ、正しい知識と指導を受けることが最短ルート。
本気で出版を目指すなら、正しい方法論に基づいて進むことをおすすめします。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
また次の記事でお会いしましょう!
この記事内容の詳細をYoutubeで語っています。ぜひYoutubeもご覧ください。