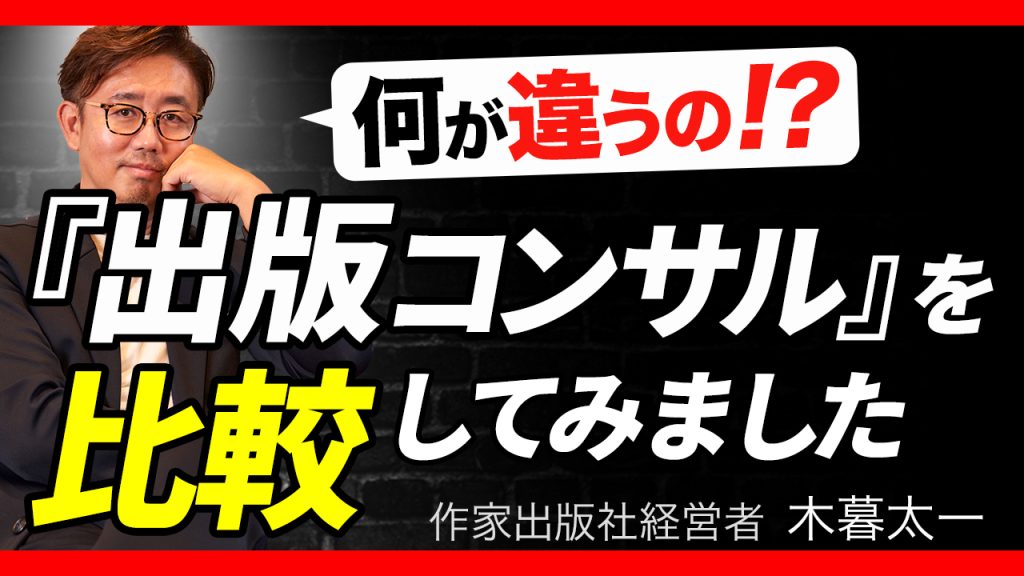はじめに
こんにちは、木暮太一です。
今日は天気も良くて気分がいいので、朝からお気に入りの大根をコトコト煮ながら筋トレして、出版のことをあれこれ考えていました。
さて、このチャンネルでは「出版業界の裏話」や「出版のリアル」についてお話ししていますが、今日のテーマは……
出版コンサルと出版塾って、結局何が違うの?
というお話です。
Kindle出版と商業出版はまったく別モノ
まず最初に整理しておきたいのが、
Kindle出版と紙の商業出版は全然違うよってこと。
Kindle出版って、自分の思いや考えを言葉にしてカタチにする作業。
誰かに認められて出すというよりは、自分の中で「これを伝えたい!」っていう想いをまとめるものなんです。
ブログを書くのと、実はそんなに変わらない。
もちろん、言葉にすること自体は素晴らしいことだし、意味があると思います。でも、
「出版された」という意味では、商業出版とは別物なんです。
出版コンサルと出版塾の本質的な違い
ここからが本題。
世の中には「出版コンサル」「出版塾」っていろいろありますよね。
で、みんないいこと言うし、実際どれを選べばいいかわからないって人も多いと思います。
じゃあ何が違うのか?
一言で言えばこういうことです:
どの“基準”をもとにアドバイスしているかが違うんです。
多くの出版塾は「先生の主観」で指導している
たとえば、出版塾の先生が「こうした方がいいよ」と指導してくれるとします。
でも、それって**先生の“好み”**でしかない場合が多いんです。
出版って最終的にジャッジするのは先生じゃなくて「編集者」であり「出版社」なんですよね。
その先生がOKでも、出版社がNGだったら意味がないんです。
編集者や出版社が見ている“判断基準”とは?
出版社って、めちゃくちゃシビアに判断しています。
どういうふうに企画を見ているかというと:
- 過去の出版実績データ
- 類似書の売れ行き
- 市場性や時流とのマッチ
こういった“裏側の数字”を見ながら判断しているんです。
僕が他の出版コンサルと違う理由
僕、実は出版社を経営してるんです。
だから、他のコンサルさんと決定的に違うのは、
出版社が実際に見ているデータを、僕も見ているということ。
つまり、出版社の編集者たちと同じ視点・同じ基準で企画を評価できるんですよ。
だからこそ、
- それは通らないからこう変えよう
- この切り口なら通りやすいよ
- 今ならこのテーマが熱い!
というように、具体的かつ的確なアドバイスができるんです。
他の出版コンサルが悪いわけじゃない
もちろん、他の出版塾の先生方も熱心にやっています。
一生懸命だし、ノウハウもある。
でも、見ている景色が違うんです。
つまり、
データの有無が結果に直結するってことです。
出版って、“勘”や“感性”だけでは通らない世界。
広告の世界で「どのバナーがクリック率高いか」ってデータ見ないと判断できないのと同じです。
なぜ僕の受講生は結果を出せるのか?
正直、みんな一生懸命なんですよ。
僕も一生懸命やってるし、受講生も本気で考えてくれてる。
でも、
「一生懸命やったから通る」んじゃない。
「正しい方向に導いたから通る」んです。
出版社の視点でディレクションしてるから、成果が出る。
その違いが、出版塾と僕の提供している出版サポートの一番大きな違いです。
この記事のまとめ
- Kindle出版と商業出版は目的もプロセスもまったく別モノ
- 出版塾や出版コンサルの多くは“先生の主観”で指導している
- 出版の最終ジャッジは出版社と編集者が行う
- 出版社は“過去データ”と“市場性”をもとに判断している
- 僕は出版社を経営しているから、そのデータをもとに同じ目線でアドバイスできる
- 結果が出るのは、一生懸命だからではなく、正しく導くから
出版業界には、まだまだたくさんの「知られていない裏側」があります。
これからも、そういったリアルな情報をお届けしていきます。
この記事内容の詳細をYoutubeで語っています。ぜひYoutubeもご覧ください。