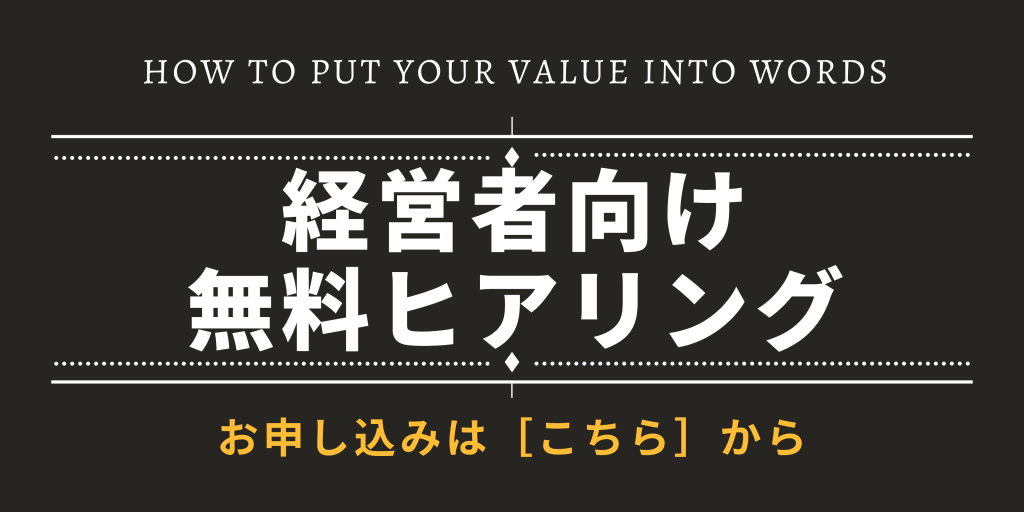言語化診断を実施いただき、ありがとうございました。各タイプの傾向と対策を解説しました。ビジネスの価値は言葉で伝え、言葉で理解してもらえなければ、評価してもらえません。言語化に関するあなたの課題を確認し、修正していきましょう。
■言葉が曖昧タイプ
言葉が曖昧になる傾向があるかもしれません。そして原因は、「使っている言葉が定義されていないこと」です。重要なキーワードに対して自分なりの定義づけをしてみましょう。
●弊害となるシーン
一番の弊害は、自社の価値が伝わらないことです。一生懸命伝えているつもりでも、言葉が曖昧なので、ほとんど伝わっていないケースがあります。
たとえば先日、こんなケースがありました。
貴社の強みは?と聞かれて、「顧客と深くコミュニケーションし、寄り添うことです」と答えた経営者さんがいました。これでは、この会社さんが何をしてくれるのか、実際に他社と比べてどのくらい「強い」のかがわかりません。
●では、どうすればいいのか?
この場合、自社が重要視している「深くコミュニケーションする」「寄り添う」という言葉を明確にしなければいけません。そして、明確にするとは、この意味を定義することです。自分にとって「深くコミュニケーションをする」とはどういうことを指すのか、何をすることが「寄り添う」ことになるのか、それを表現しなければいけません。
●言語化フレームワーク
「定義する」とは、「必要要素をリストアップすること」です。どんな要素を満たしていたら「その状態になった」と言えるのか、その必要要素を挙げることが「定義する」ということです。
今回の場合、「深くコミュニケーションする」を定義する場合、どんなことをしたら「深くコミュニケーションした」と言えるのかをリストアップします。
たとえば、
・相手と3時間以上話す
・相手の考えで納得できないことを10個以上あげ、互いに説明し合う
・お互いに遠慮して言わないことを5個ずつ言い合う
などです。自社にとっての「深いコミュニケーション」を満たすために必要な要素を出します。これが「定義する」ということです。
■キャッチコピータイプ
言語化に関して、一番の課題は「初見のインパクトを重視しすぎていること」にあるかもしれません。じっくり伝え内容を理解してもらおうとする視点を追加すれば格段に改善しそうです。そのための対策は、まず「あなたの商品の価値を言語化すること」です。
●弊害となるシーン
キャッチコピーのように「短く印象に残る言葉」を作りたいと感じる方は多いかもしれません。ですが、キャッチコピーはその名称の通り「キャッチする(つかむ)ための言葉」です。ビジネスで「つかむ」ことは大事ですが、つかんだだけでは評価されませんし、商品も売れません。
●では、どうすればいいのか?
そのあとに自社商品の価値を伝える必要があります。キャッチコピーを作ったとしても、自社の価値を言葉にできていなければビジネスにはなりません。
●言語化フレームワーク
価値を言葉にするためには、まず価値とは何か?を言葉で捉えなければいけません。
ビジネスにおける価値は大きく分けて3種類です。
1.価値は変化である:顧客に変化を与えれば「価値」になる
2.価値はテンションである:顧客のテンションを上げるものは「価値」になる
3.価値はこだわりである:顧客が異常さを感じるまでの「作り手のこだわり」は「価値」になる
の3つです。まずは貴社が顧客に提供している価値の種類を判断し、それを言葉にしてみましょう。
■熱意ありすぎタイプ
「顧客が知りたいこと」よりも、自分が伝えたいことが先に来てしまっているかもしれません。人は自分が知りたいことしか興味を持ちません。対策として、「顧客が課題を解決できない理由」を言葉にしてみることをおすすめします。
●弊害となるシーン
ひと言でいえば、「顧客を置き去りにしてしまう」という点が大きいです。自社の商品の素材や技術など「顧客にどうしても伝えたいこと」を先に語ってしまうケースがあります。ですが顧客にはその意味と意義が伝わらず、「意味不明な退屈な話」が続くことになり、商談時のトーンが下がってしまいます。
●では、どうすればいいのか?
経営者本人としては、顧客にメリットがある話をしている意識があります。しかし顧客からするとそうはなっていません。そのため、視点を変えなければいけません。「顧客に価値がある話をする」ではなく、「顧客がこれまで自分の課題を解決できなかった理由」を先に伝えてあげるようにしましょう。そうすれば、なぜ貴社の素材や技術が重要なのか、なぜあなたの話を聞くべきなのかを理解してもらえます。
●言語化フレームワーク
顧客はあなたの商品・サービスに興味を持っています。だからこそ話を聞こうとしているわけです。しかし、顧客の頭の中には「似たような商品が他にもあるし、前にも同じようなものを使ってみたけど改善できなかった」という想いがあります。
あなたが語るべきことは、「(その課題を解決するために)既存の商品だと有効ではありません。なぜなら~~~~だからです」とフレーズで理由を伝えることです。
■ライバル意識しすぎタイプ
もしかしたら、自社とライバルとの比較をする視点が強く、そのせいで顧客目線を見失っている可能性があります。まずは顧客が望むことを言葉にする必要があります。「顧客が現状不満を抱えていること」をリストアップしてみましょう。
●弊害になるシーン
商談の場で、顧客のニーズが見えなくなることがあります。ライバルを気にしすぎて、ライバルとの「差」を語ってしまうケースが多くなります。自社の商品説明時にも「A社は××という素材を使っていますが、うちは○○の素材を使います」という表現になってしまいがちですが、顧客は素材を評価しているわけではありません。結果的に、顧客がして叶えてほしいポイントに目が向かなくなってしまいます。
●では、どうすればいいのか
顧客が欲しいのは「いかにライバルと違うか」という話ではなく、「あなたは私の課題を解決してくれるか(私の願いをかなえてくれるか)」です。ライバルとの単なる「差」を打ち出しても意味がありません。一旦立ち止まって、顧客が抱えている不満に目を向けましょう。
●言語化フレームワーク
顧客が抱えている不満に目を向けるときに大事なのが「なぜそれが嫌なのか」という理由もあわせて考えていくことです(ex. 「社内で正当に評価されないのが不満。なぜなら、このままだと同期の中で出世が遅れてしまい劣等感を覚えてしまうから」)。理由が言えないものは顧客が抱えている不満ではなく、「顧客に抱えてほしい不満」であり、「自社がその商品を売りたいだけ」です。
■専門家どっぷりタイプ
相手に全ての情報を伝えようとするがあまり、言語化できなくなっている可能性があります。「初心者さん」に向けてまず何を伝えるかを決めると効果的です。自社がどの要素を一番大事にしているか言葉にしてみましょう。
●弊害になるシーン
単純に、あなたの話が難しすぎて顧客が理解できずにいます。顧客はなんとなく雰囲気を壊さないようにわかったような顔をしています。ですが、理解はしていません。そのため、決断を促しても「Yes」は出てきません。追加のプレゼンの場をもらおうとしても、顧客自身も「何がわからないかが分からない状態」のため、かなり消極的な商談になってしまいます。
●では、どうすればいいのか?
意識として、シンプルに「初心者向けの伝え方」に変える必要がありそうです。専門家は知らず知らずの間に話が難しくなりがちです。「ふつう」のことを伝えているつもりが、専門家しか分からない言葉&内容になっている可能性があります。初心者に対して伝えるとしたら、何をどう伝えるか? を振り返ってみましょう。
●言語化フレームワーク
「初心者向けに伝える」ためには、言葉を一般用語に変えるだけでは不十分です。初心者さんは前提知識を持っていないため、多くの情報を理解することが難しいです。そのため、「ここだけでいいから伝えたい」というポイントに絞る必要があります。自社のビジネスについて1つしか言えないとしたら、何を伝えますか? その「自社が一番大事にしている要素」をピックアップして伝えましょう。
言語化力を磨いて、ビジネスにレバレッジを掛けたい経営者向けに、ぼくが一緒に言葉を磨いていくマンツーマンセッションをご用意しています。詳しくは[こちら]をご覧ください。