

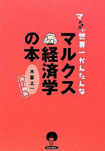 |
マルクスる? |
|||
世界一わかりやすいマルクス経済学の本
・・・・「はじめに」より・・・・・・・・・
「落ちこぼれでもわかるマクロ経済学の本」と「落ちこぼれでもわかるミクロ経済学の本」。
そしてこれが3作目のマルクス経済学の本です。
出版するのが最後になってしまいましたが、実はマルクス経済学編を一番最初に書きました。
それは単純に、「一番面白かったから」。他人に言うと、よく不思議がられます。
今ではマルクスを教えない大学も多いみたいです。
ぼくの大学ではマルクスの授業はありましたが、マクロやミクロと比べてみると、
雰囲気的にマルクス経済学を「経済学」ではなく、「歴史」と見ている部分が強いように思います。
確かにマルクス経済学を勉強しても株のデイトレードで儲けたり、
来年末の円相場を予想したりすることは難しいでしょう。
でもそれはマクロ経済学・ミクロ経済学も同じじゃないですか?
どれも経済がどのように動いているかを理解するための「ベース」にすぎません。
マルクス経済学は経済の原理、原則であるとぼくは考えています。
なぜお金がなきゃいけないのか、
なぜ商品は商品となりえるのか、
資本家はどうやって利益を得ているのか、
労働者の給料はどうやって決まっているのか、
など。
そのようなことが体系的に説明してあります。
確かに小難しい表記が多いですが、言っている事は資本主義経済、
特に日本経済にはよく当てはまりますので、現実に置き換えて考えてみると意外と分かりやすいですよ。
・・・・・・
マルクス経済学を理解するポイント。
それはズバり、「基礎用語」です。
基礎用語をしっかり理解できていれば、全体をちゃんと把握できます。
マルクス経済学は、マクロ、ミクロとは違って、計算を必要とする部分はほとんどありません。
理論を理解すればそれでOKなんです。
それゆえに、理論の基盤となる基礎用語が大事なんですね。
ここでは、本文中に出てくる基礎用語の中から特に重要なものを
ピックアップしてご紹介しようと思います。
(1)使用価値
「使用価値」というのは、「役に立つ」ということです。
「ものに『使用価値』がある」という場合には「それを使って意味がある」、
つまり「それが何かの役に立つ」ということを言っています。
例えばパンが使用価値を持つのは人がそれを食べて、空腹が満たされるから。
次に出てくる「価値」とは全然違う意味なので、注意してください。
(2)価値
「価値」というのは「使用価値」とは違って、
外見からや、使ってみたりしても分かりません。
マルクス経済学で言う「価値」とは、
「それをつくるのにどれだけ手間がかかったか」を計る尺度なんです。
だから、一般的に言う「それをするだけの価値がある」や、「一見の価値あり」とは違います。
「価値」の大きさは人がそれを作るのにどれだけ苦労したか
(どれだけそれに対して労働したか)によって決まる、つまり「価値」があるといった場合、
「この商品は、○○人で○○時間かけて作ったから、すごい価値がある。」
といった感じで、
外からは見えず、またそれが役に立つかどうかもわからないが、
とりあえず人の手がかかっている、ということでなんです。
だから、ある商品の「価値」の大きさは、
その商品につぎ込まれた「人間の労働の量」によって決まります。
つまり「価値」っていうのは「使用価値」とは違って、それがどんなものかというよりも、
それにどれだけの労働が費やされたかによって決まって、
多くの労働が費やされば「価値」が大きいということになる。
簡単に言うと、時間をかけてつくったものは「価値」が大きい、ってことです。
日常会話で使う「価値」は、マルクス経済学でいう「使用価値」の場合が多いので、
ちょっと勘違いしやすい。気をつけてくださいね。
(3)具体的有用労働
この「具体的有用労働」というのは、要するに「具体的な仕事」のことです。
これは次の「抽象的人間労働」と全く違って、具体的に、例えば靴を作る労働、
パンを作る労働、かっぱの人形を作る労働などを指します。
だからある商品の使用価値(例えば、空腹を満たすというパンの使用価値、
足を保護するという靴の使用価値、一緒にいると寂しくないというかっぱの人形の使用価値)は
パン、靴、かっぱの人形を作るという具体的な労働、つまりこの「具体的有用労働」によって
生み出されているのです。
生産物の使用価値がそれぞれ異なるのは、それを作るために違う労働をしているからです。
みんな違う仕事をしているから、違う商品が出来上がって、違う用途で使われる。
考えてみれば、自然なことですよね。
(4)抽象的人間労働
「具体的人間労働」に対して「単にエネルギーを使う」という意味での労働を
「抽象的人間労働」といいます。パンを作る労働にしろ、靴、かっぱの人形を作る労働にしろ、
結局は人が体を動かして何かを作っていることに変わりはない。
具体的に何ということではなくて、とりあえず人が働いている、
そういう漠然とした抽象的な意味での労働を「抽象的人間労働」といいます。
そして、この「抽象的人間労働」が「価値」をつくることになります。
さっき「人の手が多くかかっている方が価値が大きい」と書いたけど、
この「人の手がかかっている」というのは別に誰がどういう仕事をした、ということではなくて
「人がそれに対して、なんか知らないけど手を加えた」、という意味ですよね。
だからつまり「価値の大きさ」というのは、この「抽象的人間労働」の量によって決まっていて、
この「抽象的人間労働」が多い方が「価値」が大きいということなんです。
あとで、「抽象的人間労働が対象化されている」とかいう難しい文章が出てきますが、
これは人間の労働が、その商品(対象物)に入り込んでいる、ということで、
要するに「人の手がかかっている」ということです。
この「価値」と「使用価値」をちゃんと区別しておかないと、この先の話がややこしくなりますので、しっかり理解しておいて下さい。
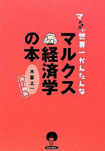 |
マルクスる? |
|||||||
〒104-8127 東京都中央区銀座2-13-20-5F
TEL:03-3542-3139
FAX:020-4623-8540
info@matomabooks.jp
www.matomabooks.jp